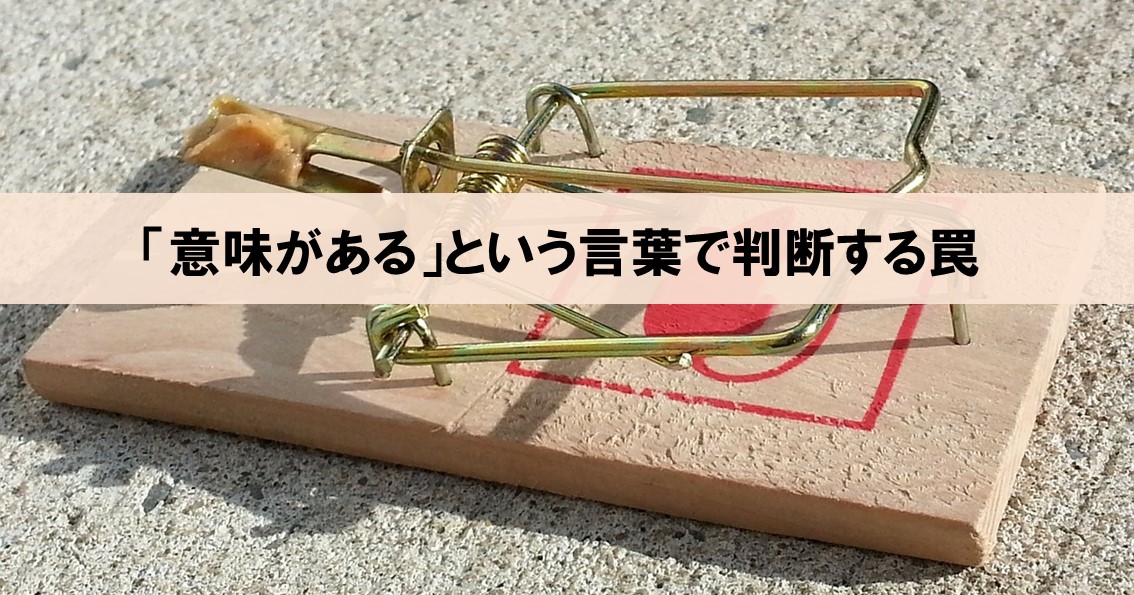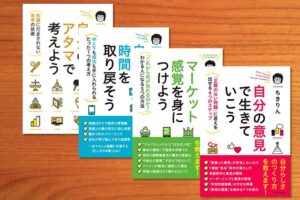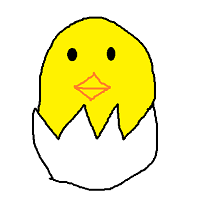突然ですが、みなさんは仕事の中で、
「こんな仕事、今やるべきなの・・・?」
と、モヤッとする場面って多くありませんか?
それを上司に聞いてみると、こう言われるのがオチです。
- 「この仕事は、〇〇という点で意味があるんだ。」
- 「これは雑務って感じるだろうが、〇〇という観点で重要なんだ。」

これを言われると部下としては、「う~ん。。」って感じだと思います・・・笑
このような場面に何度も遭遇して、気がつきました!
「仕事を、意味のアリナシで選んじゃいけない!」ということに、、!
今回は、そんな話をまとめてみます!
- どんな行動にも「意味」は必ずある
- そのため、「意味があるからやる」という理屈は、どんな行動にも当てはまってしまう
- 意味のありなしではなく、「生産性」で判断するべき
「意味がある」という言葉では、全てが正当化されてしまう!

まず結論からいうと、「この仕事は、〇〇という点で重要だ。」という判断で仕事を選ぶのは、間違いなく”NG”です。
理由はシンプルで、その判断基準だと「どんな仕事であっても正当化されるから」です。
というのも、どんな仕事であっても、意味付けをしようと思ったらできてしまうからです。
例を挙げてみます!
保険会社で働くAさんは、上司に、次のように言われたとしましょう。
上司:「今から街に行って、道行く人に100枚名刺を渡してこい。」
A:「え・・・。なんで、そんなことをするんですか、、?」
上司:「そういった行動が、新しい客の獲得につながるんだ。いずれ、この経験が活きるんだ。」
また、こんな例もあるでしょう。
社長:「毎朝、仕事が始まる前に30分の掃除を命じる。そういった些細なことが、良い仕事に繋がるんだ。」
どちらも確かにプラスの効果はあるかもしれない。
しかし、数ある仕事の中で、それは”優先的に”やるべきことなのでしょうか、、?
行動はすべて何らかの意味はある
ここで重要なのが、「世の中の行動はすべて、何かしらの意味はある。」ということ。
ぼーっとする時間も、外で散歩している時間も、仕事をしている時間も、必ず何かの意味ってあります。
そして色んな行動が、思いもつかない良い結果につながる可能性ってありますよね。
たとえ昼寝でさえも、心身がリフレッシュされて仕事のモチベーションが回復する、という効果があるため、「意味がある」「重要だ」と言えます。
このように、人間が取る行動は、どんなことでも「意味がある」と言えてしまうんです。
よって、「これは意味がある仕事だ。」という理論は、「当たり前」すぎる回答。
もはや「何も言っていないに等しい」んですね・・・!
仕事は「生産性」で選ぶ

「意味がある」という言葉を使うと、何でも正当化できる。
つまり、意味のありなしで判断すると、どんな行動も「正解」となってしまうんです。
ここで、「じゃあ、一体どうやって仕事を選択すれば良いの・・・?」と疑問が生まれると思います。
答えはシンプルで、「生産性で判断する」です。
説明のため、別の例を挙げてみます。
保険営業のAさんは、次の2つのどちらをやろうか迷っていたとします。
- 毎朝30分、フロアの掃除をする
- 毎朝30分、営業に関する本を読んで知識を身につけていく
仕事ができるようになるには、①と②のどちらを選ぶべきでしょうか・・・?
答えは②ということを、簡単に判断できますよね。
これは、会社の利益をあげるという目的に対して、より適した手段が②だからです。
②のほうが、「かける時間に対してリターンが大きい」=「生産性が高い行動」とも言えますね。
今回、一番言いたかったのはこれです!!
仕事を選ぶ際に何よりも大事な基準は、「生産性」なんです。
「意味があるかないか?」という判断だけでは、すべての仕事が正当化される。
それによって、仕事の取捨選択がまともにできないんですね。
しかし、「生産性」で比較すると、「AとBどっちの仕事をすべきか?」の判断を明確におこなえるようになります。
「会社のことを考えると、今はAよりBという仕事に集中したほうが、生産性が大きい!」
こういった判断を取れるようになるのが、本当の社会人だと感じています。
ホワイトカラー業務に従事する人の中には、自分たちの仕事はブルーカラー業務よりも自由度が高く、クリエイティブで難度の高い仕事だと考えている人もいます。 この根拠なき優越意識のために、ホワイトカラー部門に生産性向上のための研修や新制度を導入しようとしても、「効率ばかり追い求めていては、いい仕事はできない」などといった心理的な抵抗に阻まれることがよくあります。
(引用:『生産性』 Kindle位置=432)
まとめ
今回は、「意味がある」という判断で仕事を選ぶのは危険だという話をまとめてきました。
- 「こんなことを長時間続けて、本当に意味あるのか?」
- 「この時間があるなら、他に時間を割いたほうが有用だろ、、。」
みながそう思っているのに、その仕事が長期間続けられているなんていう状況は、もはや地獄でしかありません、、。
「意味がある」という無意味な判断ではなく、「生産性」という明確な基準で仕事を選べるようになりたいですよね!
- どんな行動にも「意味」は必ずある
- そのため、「意味があるからやる」という理屈は、どんな行動にも当てはまってしまう
- 意味のありなしではなく、「生産性」で判断するべき
ちなみに、「生産性」についての話であれば、下記の本は”間違いなく”おすすめできます!!!
まさにそのために日本では、生産性という概念がまるで「工場のオペレーションの効率化の話」であるかのように捉えられてしまっています。 それ以外の分野における生産性への関心の低さは、国際的な産業別の生産性比較の結果にも顕著に表れています。
(Kindle位置:38)
「生産性」という言葉は”意識高い系”に聞こえてしまいますが、重要な概念であることは間違いない!強くそう思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!