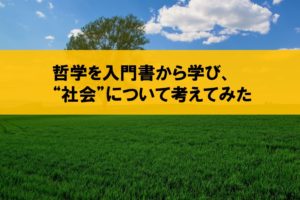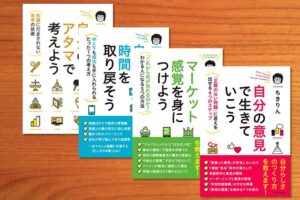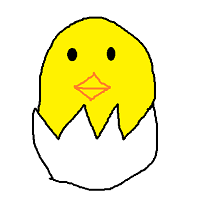こんにちは、読書大好きサラリーマンのネルです。
「何だこの本!初めて読んだジャンルだったけど、めっちゃ面白いな!!」
読書していると、時々こういった「嬉しい発見」ってありませんか?
読書好きの多くは、例外なく「好きなジャンルの本」があるはずです。
本屋に行くと、いつも似たような本を手にとってしまう、というのは”あるある”ですよね…笑
しかし、「何気なく手にとってみた本だったけど、めっちゃ面白い!」という発見も、読書の大きな楽しみだと強く思っています。

その「意外な発見」を得るため、自分はこれまで”色んなジャンルの本”にトライしてきました。
そんな中で、「これは、ぜひとも他人におすすめしたい!」と思える本にも、沢山出会ってきたんですね。
そこで今回は、これまで1,000冊以上は読んできた沢山の読書記録から、「新たな価値観を得られた!」「視野が広がった!」という本をまとめていきたいと思います!
【目次】
価値観が広がる本
さっそく結論からお伝えします。
自分の価値観・視野を広げてくれる超おすすめの本は以下の通りです。
- 「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
- 武器になる哲学
- 人間の性はなぜ奇妙に進化したのか
- 社会心理学講義
- 最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常
- 自閉症の僕が跳びはねる理由
- 利己的な遺伝子
- 怖い絵
- 正義の教室 善く生きるための哲学入門
- 働かないアリに意義がある
- 予想どおりに不合理
- アムンセンとスコット
- 常識として知っておきたい裏社会
順番にテンポよく紹介していきますね!

「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
【難易度:小】
まずは、つい最近読んだこの本。
面白いポイントは、ぼくらが抱いているアートへの偏見・常識を、ことごとく”先回り”してぶち壊してくれることです笑
その男の子は、作品名だとか解説文といった既存の情報に「正解」を見つけ出そうとはしませんでした。むしろ、「自分だけのものの見方」でその作品をとらえて、「彼なりの答え」を手に入れています。
(Kinlde位置:38)
「ピカソの絵って、下手くそなのに、あれだけ人気ある理由がわからんわ・・・。」
もしあなたがそう思っているならば、この本を今すぐ手に取るべきです!

武器になる哲学
【難易度:中】
哲学を学ぶと「役に立つ」とか「カッコいい」とか「賢くなる」ということではない。
哲学を学ばずに社会的な立場だけを得た人、そのような人は「文明にとっての脅威」、つまり「危険な存在」になってしまうというのがハッチンスの指摘です。
(Kindle位置:36)
あなたは、「哲学って、どうせ、昔の人が”ヘリクツ”をこねていた学問でしょ・・・?笑」と感じてはいないでしょうか。
本書を読むと、「哲学的に考えるって、こういうことか、、!たしかに、便利かも・・・!!」と感じられると思います。
「哲学なんて、わけ分からんものなんて知らん!」って方へ!!
そういう人にこそ、本書はめちゃくちゃおすすめです!!

人間の性はなぜ奇妙に進化したのか
※本書の表紙は少しだけ過激なので、本記事には貼っていません。内容に興味のある方は、リンク先で確認してください・・・!
【難易度:中】
人間もあくまで「動物の1種」である。
そう冷静に捉え、”性”に関する話を科学的に分かりやすく展開してくれます。
- なぜ男性は、浮気性ばかりなのか?
- なぜ女性のほうが、子供に愛情深い人が多いのか?
これまで、こういった「疑問」を少しでも抱いたことがある人は、読んでみることを強くおすすめします。
知的なパラドックスである。自然淘汰の本質は、より多くの子孫を残すような形質の遺伝子が広まることである。
それなのに、なぜ自然淘汰によって、一つの生物種のすべてのメスが、多くの子孫を残す能力を失わせる遺伝子を担うようになったのだろうか?
(Kindle位置:1,723)
生物学の知識を吸収していくと、
「なるほど、、。だから、男性はこうで女性はこうなのかもな・・・!」
と納得できる箇所が間違いなく見つかるはずです!

社会心理学講義
【難易度:高】
何より特徴的なのは、「今すぐ使える心理学!」みたいな生易しい本”ではない”、という点です。
「人は、どのような感情を抱き、どう行動する生き物なのか」を考えるうえで、非常に参考になるような話が書かれています。
理論の正しさを確かめるために実験をするのだと普通信じられていますが、その発想自体がつまらない。
逆に、理論の不備を露わにすることで、慣れ親しんだ世界像を破壊し、その衝撃から、さらに斬新な理論が生まれるきっかけを提出することこそが実験に本来期待されるべき役割です。
(Kindle位置:595)
紹介されている実験内容によっては衝撃を受けたりして、知的好奇心がぐいぐいと刺激されます。
「人間はこうです。」とか、よくある言い切りではない。
様々な研究を引用しながら、
「・・・と、一般には考えられているが、研究結果から考え直すと、人の本質ってこうかもよ・・・?」
という「ハッとさせられる主張」が次々に展開されていくのが特徴です。

心理学系の本って、「知的好奇心」をグイグイくすぐってくれますよね、、笑
最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常
【難易度:小】
「音楽環境創造科には、『自己表現』って試験科目があるのよ」 音校卒業生の柳澤さんが、同級生の逸話を教えてくれた。
「自己表現……?」
「何でもいいから、自分をアピールするの。私の友達は、ホルンで四コマ漫画をやったわ」
「えっ、どういうこと?」
(Kindle位置:570)
今回取り上げた本の中でも、かなり読みやすい本なので安心してください。
「世の中には、こんな独特の世界観の場所があるのか・・・。笑」
驚き、という意味では、紹介する本のなかで圧倒的に一番な本です、、!!

自閉症の僕が跳びはねる理由
【難易度:小】
著者は重度の自閉症なので、本を書くのは普通であれば難しいです。
そこで、「特殊な機械」を使って、長い時間をかけて本書を書きあげてくれたのです・・・!
多くの人にとって、「自閉症の人の意見を聞く」という体験自体が、非常に貴重なことなのではないでしょうか。
赤ちゃん扱いされるたびに、みじめな気持ちになり、僕たちには永遠に未来は訪れないような気がします。 本当の優しさというのは、相手の自尊心を傷つけないことだと思うのです。
(Kindle位置:182)
「ぼくが辛いのは、周りから”赤ちゃん”のように扱われること。」
この一文にハッとさせられました。
知的障害を持った方に、”赤ちゃん言葉”で接してしまっている人って、かなり多いのではないでしょうか・・・。
この本を読むことで、自閉症の方が普段何を感じ、何に苦しんでいるのかを知ることができます。

利己的な遺伝子
【難易度:高】
生物学の名著で、「タイトルだけは聞いたことがある。」という方が多いのではないでしょうか。
「利己的」というタイトルを見ると、
「ふつうの動物と違って、人は利己的なだけではなく、他人への優しい心も持っているだろ!!」
知性をもつ人間として、こう主張したい気持ちはよく分かります。
しかし本書では、以下のようにバッサリと言い切っているんですね。
よく調べてみると、利他的に見える行為はじつは姿を変えた利己主義であることが多い。
(Kindle位置:574)
とても冷たい主張ですが、なぜそう言えるのか・・・?
「遺伝子が生き延びるためには、利己的であることが必要だから」と、著者はバッサリと言い切っています。
この主張について詳しい内容が気になる方は、ぜひ本書にチャレンジしてみてください!
「遺伝子」とは、一体どういうものなのか?じっくりと考えさせられる本です。

怖い絵
【難易度:小】
「まずは、この絵を見てください。何か感じることがありますか?」
↓↓↓
「実はこれは・・・(略)」
という展開で、「絵と解説のセット」で次々に紹介されていきます。
タイトルが「怖い絵」とありますが、お化けとかゾンビとか、そういった”非科学的な怖さではない”のが大きな特徴です。
その絵が描かれた歴史的背景や、画家の特徴をしっかりと解説しながら、「その絵にどんな意味が込められているのか」を、初心者にもわかりやすく説明してくれるんですね。
その解説を読んだあとに絵を見返すと、「最初に見たときとは全然違った見え方になる」という点が何よりも面白いです。
一番恐ろしいのは天変地異でも幽霊でもなく”生きた人間”だと肝に銘じた者にしか、『いかさま師』のぎろりとした横眼は描けなかったのかもしれない。
(Kindle位置:210)
1冊目で「アートの見方」についての本を紹介しましたが、本書では、「知識があることで、アートの楽しみ方がぐんと広がる」ということを体感できると思います。

正義の教室 善く生きるための哲学入門
【難易度:小】
「確実に”正義”ではない、と言えることが一つだけある。それは、何が正義かを事前に決めつけること」
著者「飲茶さん」は、初心者向けの哲学本を書くベストセラー作家として、非常に人気のある方です。
著者の本の中でも、この「正義の教室」は、哲学の知識がなくても、読んでいく中で一緒に考えを巡らせる体験がしやすい、本です。

働かないアリに意義がある
【難易度:中】
「働かないアリに意義がある」なんて、”ワクワク”するタイトルだと感じるのは、私だけでしょうか・・・?笑
つまり誰もが必ず疲れる以上、働かないものを常に含む非効率的なシステムでこそ、”長期的な存続が可能”になり、長い時間を通してみたらそういうシステムが選ばれていた、ということになります。
(Kindle位置:759)
ビジネスの場で、「働きアリの法則」とか、「2:8の法則」なんて言葉を聞いたことがあるかもしれません。
一般的に、アリも人も、「組織の中で一定割合は、必ず”サボる”メンバーが出てくる」という理論ですね。
本書を通じて、
「こういうサボるメンバーがいるからこそ、もしかしたら組織はうまく回っているのかもしれない。」
そう考えるきっかけを得られます。

予想どおりに不合理
【難易度:中】
紹介を兼ねて、本書から1つ「例」を出します。
仮に、あなたが「レストランのオーナー」だったとします。
「お店で一番売りたい高級メニュー」があるとしたら、あなたは、どんなことをすべきだと思いますか?
その答えは、「一番売りたいメニューよりも、少し高い”おとり”メニューを1つ設定する」というのです。
たいていの人は、メニューのなかでいちばん高い料理は注文しなくても、つぎに高い料理なら注文するからだ。
そのため、値段の高い料理をひとつ載せておくことで、二番めに高い料理を注文するようお客をいざなうことができる。
(Kindle位置:312)
こういった「人間心理」と「経済学」の知識をあわせた分野は「行動経済学」と呼ばれ、沢山の本が出版されています。
中でも、下記の『影響力の武器』という本が一番有名ではないでしょうか。

本書も非常に面白いですが、「初心者に読みやすく」「文章にひねりがあり、くすっときて面白い」という点で、どちらも未読の方には、『予想通りに不合理』をおすすめします。

アムンセンとスコット
【難易度:小】
本書は、「人類の南極点の初到達」を目指して、2つの探検隊が争った”事実”をもとに書かれた本です。
南極点という「マイナス50度」の極限の環境。
2人のリーダーはどんな思いで、どうやって南極点まで隊員をリードしたのか。
そして結果はどうなったのか・・・?
ただのビジネス本ではなく、「歴史的な事実」であるからこそ、「極限の環境では、リーダーはどんな役割が求められるのか?」ということを学べる最良の本です!
「やってみるか?」と隊長が言ったとたん、四隊員は大喝采でこれに応じ、たちまちに荷造り開始。
アムンセンはこの朝の隊員たちの劇的な反応ぶりに感動して、その不屈の精神をたたえ、この瞬間の情景がのちのちまでもまぶたから消えなかったと手記に書いている。
かくて五人はブリザード(猛吹雪)のなかへ出発していった。
(文庫版ページ:170)

常識として知っておきたい裏社会
【難易度:小】
「裏社会」
この言葉は時々耳にすると思いますが、正直、「この治安の良い日本に、本当にあるの?」とすら思ってしまいますよね。
しかし、実際には残念ながら存在するんです・・・。
特に、最近は「闇バイト」で捕まる若者がチラホラ出ていますが、ああいったものも、その背後には「裏社会」の人たちが大きく関わっています、、。
下記は、「振り込め詐欺」でたまにあるケースだそうです。
それから、ターゲットと電話をしていて、途中で詐欺だと発覚するケースがあるじゃないですか。
そういうとき、グループによっては、開き直って「かなわないなぁ、どこからバレてました?(笑)」って聞くらしいんですよ。
すると不思議なことに、ターゲットの方も、「この辺が怪しかった」みたいな話を和気あいあいとしちゃうんですよね。
そんな感じで和やかに電話が終われば、警察にチクられるリスクも減るし、反省点も明確にわかる。
「ここがダメだった」ってリアルなダメ出しをもらえるわけですからね。
(Kindle位置:1,306)
本書で初めて知ったのですが、著者のお二人は、裏社会について語る人気YouTuberだそうです。
語ってくれる内容がかなりリアルで、「本当に裏社会を経験してきた人たちだからこそ知っている情報」が盛りだくさんでした。
「自分の身を守るためにも、知っておくべき知識」という意味で、かなり強くおすすめする本です。

まとめ
今回は、「価値観・視野が広がる本」を紹介してきました。
普段から、ベストセラー本・人気本を中心に読んでいる方でも、「これ系の本はあんまり読まないな~。」なんて場合が多いと思います。
まさにそんな方にこそ、本記事から1冊でも気になった本を読んでいただき、「たしかに、こういった本もめちゃくちゃ面白いかも・・・!」と体験してくれると嬉しいです!
今後も色々な本を読んでいくので、また面白い発見があったら当ブログで紹介していきますね!
- 「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考
- 武器になる哲学
- 人間の性はなぜ奇妙に進化したのか
- 社会心理学講義
- 最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常
- 自閉症の僕が跳びはねる理由
- 利己的な遺伝子
- 怖い絵
- 正義の教室 善く生きるための哲学入門
- 働かないアリに意義がある
- 予想どおりに不合理
- アムンセンとスコット
- 常識として知っておきたい裏社会
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!