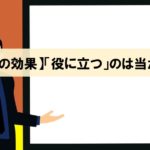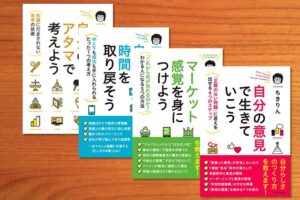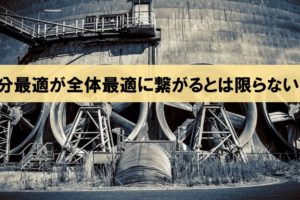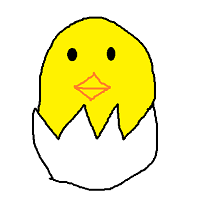「フロギストン」という言葉を、皆さんは聞いたことがありますか?
フロギストンとは、「物が燃える際に消費される物質」のことで、18世紀に世界的に信じられ、今はその存在自体が否定されています。
今回は、フロギストンの説明と、そこから分かる「常識に縛られる危険」をテーマに話をまとめていきたいと思います。
参考にした本は、小坂井敏晶『社会心理学講義』です。
- 人は「常識」に縛られると、事実を受け止められなくなる
- 過去には、フロギストンという「負の重量」を持つ物質が信じられていた
- 事実と理論が異なったときに、事実を受け止める姿勢が重要
それでは、順番にポイントをまとめていきます!
常識に縛られる危険
「常識に従うことは大切だ」という意見は多いですよね。
社会で生きていくためには、常識を把握し、上手に立ち回らなければいけないこともあると思います。
しかし、今回紹介するのは、「常識に縛られた思考をしてしまう危険」についてです!
常識を無批判に信じてしまっていては、冷静な判断ができなくなるのです。
その面白い例が、「フロギストン」という物質を巡る話です。
「フロギストン」とは?
フロギストンとは「ものが燃える際に消費される物質」のことです。
とはいっても、18世紀ごろに信じられていた説であって、現代ではこの物質の存在は明確に否定されています。
18世紀、科学者たちは次のようなことを考えていました。
「そもそも、ものって何で燃えるんだろう・・・?」
今でこそ、「ものが燃えるとは、空気中の酸素と結びつく反応のことだ。」と小学校で習いますが、当時はこんなことは全くわかっていなかったんですね。
そこで、18世紀のドイツの科学者ゲオルク・シュタールが、考え出したのが、「フロギストン」と呼ばれる物質です。
「モノが燃えると、その中に含まれる”フロギストンが消費”される」という説で、当時では世界的に有力な説でした。
モノが燃えるのは、その中に含まれている特定の物質が消費される、ここまでは確かに納得できる説ではあります。
しかし、主に金属においては、「燃えると重くなる」という性質があります。

当時も、実験によっては、この事実は知られていました。
シュタールの説では「モノが燃えるとは、フロギストンが消費されること」ということでした。
すると、フロギストンが消費されているのに、”重くなる”というのは、明らかな「矛盾」が生じることになりますよね。
フロギストンは負の重量を持つ!?
それでは、シュタールはこの矛盾にどう向き合ったのか。
なんと、自分が打ち立てた理論があくまでも正しいということを疑わず、こんな説明をしました、
「そうか、、!フロギストンは、負の重量を持つのか!だから、モノが燃えてフロギストンが消費されると、そのモノは重くなるのだ」
負の重量・・・笑
数学的に見ると、つじつまは確かに合いますが、では「負の重量」って現実にどう存在するの?手で持ったら、どんな感じなの?
と、疑問でいっぱいになりますよね・・・笑
しかし、なんと18世紀末に新しい理論が発見されるまでは、その「負の重量」という概念が世界的に正式に認められていたのです!

常識と反する事実を受け止められるか
今でこそフロギストンの話は、昔の「笑い話」のように聞こえます。
しかし、その時代では世界的に見ても有力な説であり、「当時の常識」となっていたわけなんです。
「モノが燃えるのは、フロギストンが消費されているからだ」という説を、揺るぎない事実として信じ込んでしまった。
そこから妙な事実が見つかっても、その説を曲げないよう「負の重量」という無茶な説明がされていった、というわけなんですね。
この話から、「常識が誤っているかもしれないと思う態度」が重要であることがわかります。
理論とは違う「現実」が起こった場合には、その理論を根本から疑う姿勢を常に持つことが、時には重要なんですね!
「自分が信じていることや社会で常識とされていることも、もしかしたら誤っているかもしれない」という柔軟な態度を持ち続けていきたい、そう思わせてくれる事例でした。

まとめ
今回は、「フロギストンの説明と、常識に縛られる危険」についてまとめていきました!
「負の重量」などというおかしな学説がほんの数百年前まで信じられていたことに素直に驚くのではないでしょうか。
しかし、時間がたった現代だからこそ、「それはおかしい」と指摘ができるわけです。
そう考えると、もしかしたら、今私達が信じている科学の多くは間違っており、数百年後には修正されていくのかもしれない、という知的態度を持っておきたいですね!
- 人は「常識」に縛られると、事実を受け止められなくなる
- 過去には、フロギストンという「負の重量」を持つ物質が信じられていた
- 事実と理論が異なったときに、事実を受け止める姿勢が重要
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!