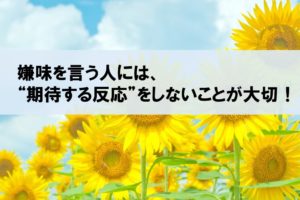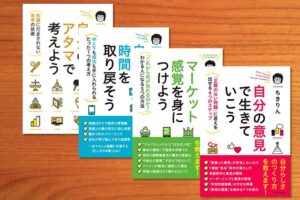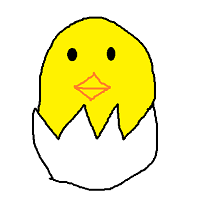こんにちは読書ブロガーのネルです!
皆さんは、ほしい本を見つけたとき、こんな迷いが生じたことはないでしょうか。
「紙の本か、電子書籍か、どっちで購入するか迷う・・・。」
この話は奥が深い問題で、それぞれメリット・デメリットがあるため、簡単には決めきれない話だと思っています。
- 紙の本は、質感を感じながら読めるし、自由にメモを書き込める。また、読み終わったあと人に貸せたり、売ることもできる。
- 電子書籍は、保管時に場所を取らないし、持ち運びも便利。マーカー機能をつかえば、あとからパパッと重要箇所を見返せる。
「どちらを買うかは、個人の趣味」と言ってしまえばそれまでなんですが、「他人がどういう基準で判断しているのか?」を知ることは、自分の軸を決めるときに有用だと思います。
そこで、一例として、自分自身がこれまで考えてきた「紙の本vs電子書籍の使い分けルール」を紹介してみます!
それによって、「ああ、たしかにそういう考え方もあるのか~」という気付きを得てもらえたら、という思いでまとめていきます!

本購入の際「紙か電子書籍か」決める基準

まず私自身は、購入する本の95%ほどは「電子書籍」です。
Kindleの「ハイライト機能」が何よりも気に入っていて、「あとから重要箇所のみ見返すことができる」という点で、紙の本のメリットを遥かに上回っていると感じているからです。
しかし、電子書籍をメインで使ってはいても、”ある条件”を満たした場合のみ、紙の本を買うようにしています。
その条件とは次の通りです。
- 紙の本しか出版されていない本
- 資格の勉強本
- 画像が多い本
- 中古で安く出回っている小説
つまり、「上の条件を満たす場合は紙の本を買う。満たさなければ、Kindleで買う」というのが、私の「判断基準」ということになります。
この判断基準について、順番に解説していきます。
1.「紙の本しか出版されていない本」
「紙の本しか出版されていない本」は、電子書籍では読めないため仕方なく紙の本で買います。
めちゃくちゃ当たり前の話ですが、、笑
いわゆる「名著」と呼ばれる昔の本は、紙本しかない場合があるので、仕方なく紙の本を購入しています。
2.「資格の勉強本」
続いて、「資格の勉強本」も、紙の本で買います。
理由は、「ページを行ったり来たりすることが多いから」です。
通常の読書と違って、資格用の本は、練習問題を解きながら何度も同じページを開いたりしますよね。
つまり、ページが「あっちに行ったり、こっちに行ったりする」わけです。
また、資格用の本は、メモや計算式を書き込むことも多いですよね。
ページをパラパラめくったり、自由なところにメモを書くことは電子書籍では非常にやりにくいため、紙の本を買っているわけです。
3.「画像が多い本」
「画像が多い本」も、紙の本を意識して選ぶことをおすすめします。
たとえば、デザインを学ぶ本で、中身にイラストなどが豊富に載っているものですね。
「電子書籍は、画像が見づらい、表示速度が遅い」というデメリットがあるため、こういったものは紙の本が圧倒的に勝っていると感じています。

4.「中古で安く出回っている小説」
最後は、「中古で安く出回っている小説」かどうか?という条件です。
この点が、今回一番お伝えしたかった重要ポイントでもあります。
なぜ、中古で安く出回っている小説だと、紙の本を買う、という判断をするのか。
それは、電子書籍の「時間がたっても値段が下がりにくい」特徴が原因です。
紙の中古本は、大ヒット小説でも数年ほど経てば「1冊100円~300円」ほどでブックオフで売られるようになります。
つまり、紙の小説は時間が経てば、圧倒的に安く購入できるわけです。
一方で、電子書籍では数年以上前の小説の値段を見ても、そこまで値段が落ちていないのが現状です。
「電子書籍も値下げセールとかしてるよ!」と思われるかもしれませんが、ブックオフなどの古本屋と比較したときに、「値段の下がり具合がどうなっているか?」という点に着目してほしいです。
値下げセールと言っても、元値800円が500円に値下がり!というレベルです。
紙の中古本の100円、200円の圧倒的な安さと比べたら、大きく負けてしまっているんですね。

また、なぜ「中古で安く出回っている”小説”」と、小説に限定した表現をしたかというと、ビジネス書などの場合は、紙の本であっても意外と値段が落ちないからです。
ブックオフ店内を一周してみるとわかりますが、人気小説が100円~300円まで値段が下がっているのに対して、ビジネス書は元値1,500円が900円ぐらいにしか値下がっていないものが多いです。
人気小説はビジネス書の何倍、何十倍も売れて中古市場にも出回るため、価格がぐっと落ちやすい構造だからだと推測しています。
こういった背景があるからこそ、中古で安く出回っている「小説」は紙で買う、という表現をしたのです。
本当は、全てを電子書籍で済ませたい

以上、電子書籍ではなく「紙の本を選ぶ基準」を4つ紹介しました。
ただし、「できれば全てを電子書籍で買えるようにしたい」というのが本音です。
なんていっても、電子書籍は、
- 「保管の場所を一切取らず、いつでもどこでも読める」
- 「重要箇所をあとからパッと見返せる」
などのメリットが、圧倒的に紙の本より優れていると個人的には強く感じています。
だからこそ、電子書籍も今後、次のように変わっていってくれることを期待しています。
- 世の中のすべての本を電子化
- ページをめくる速度を上げ、パラパラ読みを簡単にできる機能をつける
- 画像の表示速度も上げ、画像の表示倍率を簡単に変えられる機能をつける
- 古本屋で安く売られているような本は、電子書籍も値段をぐっと下げる
これらが実現すれば、電子書籍のデメリットがほぼなくなり、これまで以上に電子書籍の有効活用ができると思っています!
最後に、おすすめ本の紹介です。
下記の本は、「Kindleの機能を最大限活かすためのノウハウ」がまとめった本です。
「Kindleってよく聞くけど、何が良いの?」とメリットを詳しく知らない方は、時間のあるときにこちらを一読されることを強くおすすめします!
今までずっと紙の本一択だった人も、Kindleのメリットを知ることで、Kindleを愛用することになる可能性も大いにあると思いますよ!
電子書籍、もっと進化して欲しい!